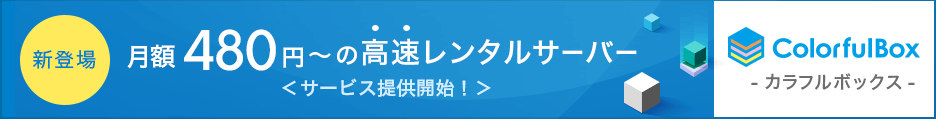
このページでは、南河内以外の地域で開催されているイベントのうち、
おがみが個人的に関心があるものをご紹介します。

|
●ところ:奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 ●期間:1998.10.10(土)~11.15(日) ●入館料:大人:800円、高校生・大学生450円、小中学生:300円、(団体:一般500円、高校生・大学生350円、小中学生:250円、※団体は20名以上) ●休館日:月曜日 ●開館時間:AM9:00~PM5:00(入館はPM4:30まで)、金曜日・土曜日はPM9:00まで ●交通案内:近鉄畝傍御陵前下車徒歩5分。近鉄橿原神宮前下車徒歩15分。 ●問い合わせ先:同館 (TEL:0744-24-1185 奈良県橿原市畝傍町50-2) ●展示概要: 橿原考古学研究所設立60周年を迎えるにあたり、その間に発掘調査した代表的な前期古墳の出土品を中心に展示。 三輪山の麓に造られた箸墓古墳に代表される、奈良盆地東南部(オオヤマト地域)の古墳の出現過程を、墳丘の形と埴輪・埋葬施設の定型化への歩みに沿ってとらえる。 さらに、この時期の王権を象徴する鏡・石製品・鉄製武器の副葬品の組み合わせについて、畿内と周辺地域の古墳との比較を通じて、各地域の勢力との政治的な連合を背景として、3世紀後半以降に営まれたヤマト王権の権力構造の実態を考察する。 (※特別展チラシより引用・一部改変) |
●関連イベント:
|

|
●ところ:堺市博物館 ●期間:1998.10.3(土)~11.8(日) ●入館料:大人:500円、高校生・大学生300円、小中学生:50円、65歳以上・障害者手帳を持つ方:無料、(団体:一般350円、高校生・大学生200円、小中学生:30円、※団体は20名以上) ●休館日:10.5・10.12・10.19・10.26・11.2・11.4 ●開館時間:AM9:30~PM5:15(入館はPM4:30まで) ●交通案内:JR阪和線百舌鳥駅下車、西へ徒歩約6分。南海高野線堺東駅から南海バス(3番乗り場)に乗車し、堺市博物館前下車 ●問い合わせ先:同館 (TEL:0722-45-6201 ZIP:590-0802 堺市百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内) ●主要展示品: 重要文化財 行基菩薩坐像(唐招提寺) 行基菩薩坐像(東大寺) 重要文化財 高僧像(仁和寺) 重要文化財 先徳図像(東京国立博物館) 重要文化財 四聖御影(永和本・東大寺) 重要文化財 東征絵巻 巻二(唐招提寺) 重要文化財 東大寺大仏縁起絵巻 上巻(東大寺) 重要文化財 大寺縁起 中巻・下巻(開口神社) 重要文化財 南瞻部洲大日本国正統図(唐招提寺) 重要文化財 日本図(嘉元三年奥書・仁和寺) 重要文化財 日本図(称名寺) 行基墓誌(奈良国立博物館) 重要文化財 続日本紀(名古屋市蓬左文庫) 重要文化財 僧綱補任 重要文化財 大般若経 巻91(常楽寺) 国宝 日本霊異記 中巻(来迎院) 国宝 三宝絵詞(東京国立博物館) 重要文化財 日本宝花験記(宝寿院) 重要文化財 東大寺要録続録(東大寺) 重要文化財 感身学正記(西大寺) 重要文化財 忍性書状(多田神社) 重要文化財 金銅舎利容器(唐招提寺) 重要文化財 弥勒菩薩坐像(孝恩寺) (※期間中に展示替えを行う。) |
●関連イベント:
|

|
●ところ:大阪府立弥生文化博物館 ●期間:1998.10.3(土)~11.29(日) ●入館料:大人:600円、高校生・大学生:400円、中学生以下・65歳以上・障害者手帳を持つ方:無料、(団体:一般480円、高校生・大学生320円、※団体は20名以上) ●休館日:月曜日(11.23は開館、11.24は休館) ●開館時間:AM10:00~PM5:00(入館はPM4:30まで) ●交通案内:JR阪和線天王寺駅から25分「信太山」駅下車徒歩7分、南海本線「松ノ浜」駅下車徒歩20分 ●駐車場:無料駐車場あり。乗用車80台分・大型バス7台分。 ●問い合わせ先:大阪府立弥生文化博物館 〒594-0083 和泉市池上町443 TEL0725-46-2162 ●主要展示品: 佐賀県菜畑遺跡出土玉類、石川県八日市地方遺跡出土管玉・玉つくり道具類、福岡県カルメル修道院内遺跡出土錫製ブレスレット、福岡吉武高木遺跡出土銅剣・玉類、大阪府茶臼塚古墳出土ブレスレットほか[出品総数約500点、うち重要文化財50点](期間中、一部展示替えを実施。) ●学芸員による展示解説:毎週日曜日・祝休日のAM11:00から特別展示室にて |
●関連イベント:
|

|
●ところ:神戸市埋蔵文化財センター ●期間:1998.10.3(土)~11.15(日) ●入館料:大人:200円、小中学生:100円 ●休館日:月曜日と11月4日 ●開館時間:AM10:00~PM5:00(入館はPM4:30まで) ●交通案内:三宮駅から:神戸市営地下鉄に約30分間乗車し、西神中央駅で下車、徒歩約5分。明石駅から:神戸市バス・神姫バスに約35分間乗車し、西神中央駅で下車、徒歩約5分 ●問い合わせ先:同館 (TEL:078-992-0656・0657 FAX:078-992-5201 ZIP:594 神戸市西区糀台6丁目 西神中央公園内) ●主催:神戸市教育委員会 ●主要展示品: 愛知県林ノ峰貝塚 縄文人骨、山口県土井ヶ浜遺跡 弥生人骨、奈良県長寺遺跡 弥生人骨、千葉県園生貝塚 土偶、長野県坪ノ内遺跡 土偶、長野県月見松遺跡 人面装飾付土器、滋賀県大中の湖南遺跡 木偶、大阪府溝喰遺跡 人面土器、岡山県百間川兼基遺跡 人形土製品 ●講演会: 日時:10月18日(日)PM2:00~ 「縄文人と弥生人-その時代を生きた人々の表情-」 片山一道 氏(京都大学霊長類研究所教授) |
●大野寺跡平成9年度発掘調査速報展
「土塔出土の人名瓦 -行基を支えた人々-」
●ところ:堺市立埋蔵文化財センター
●期間:1998.7.6~9.30
●入館料:無料
●休館日:土曜日・日曜日・祝日
●開館時間:AM9:30~PM5:15(入館はPM4:45まで)
●交通案内:泉北高速鉄道「栂・美木多」駅下車北へ徒歩20分、南海バス「福泉中央小学校前」下車西へ徒歩3分、南海バス「一の坂」下車東へ徒歩5分
●問い合わせ先:堺市立埋蔵文化財センター 〒590-0156 堺市稲葉1-3142 TEL0722-73-6101
●平成10年度春季企画展
「邪馬台国時代の四ツ池遺跡」
●ところ:堺市立埋蔵文化財センター
●期間:1998.4.1~6.30
●入館料:無料
●休館日:土曜日・日曜日・祝日
●開館時間:AM9:30~PM5:15(入館はPM4:45まで)
●交通案内:泉北高速鉄道「栂・美木多」駅下車北へ徒歩20分、南海バス「福泉中央小学校前」下車西へ徒歩3分、南海バス「一の坂」下車東へ徒歩5分
●問い合わせ先:堺市立埋蔵文化財センター 〒590-0156 堺市稲葉1-3142 TEL0722-73-6101

|
●平成10年度春季特別展 「縄紋の祈り・弥生の心」-森の神から稲作の神へ- ●ところ:大阪府立弥生文化博物館 ●期間:1998.4.25~6.28 ●入館料:大人:600円、高校生・大学生:400円、中学生以下・65歳以上:無料、(団体:一般480円、高校生・大学生320円、※団体は20名以上) ●休館日:月曜日(5月4日・5日は開館、5月6日は休館) ●開館時間:AM10:00~PM5:00(入館はPM4:30まで) ●交通案内:JR阪和線天王寺駅から25分「信太山」駅下車徒歩7分、南海本線「松ノ浜」駅下車徒歩20分 ●駐車場:無料駐車場あり。 ●問い合わせ先:大阪府立弥生文化博物館 〒594-0083 和泉市池上町443 TEL0725-46-2162 ●主要展示品: 山梨県安道寺遺跡出土土器(縄紋時代中期)、青森県三内丸山遺跡出土土偶(縄紋時代中期)、青森県風張遺跡出土土偶(重要文化財・縄紋時代後期)、宮城県沼津貝塚出土遺物(縄紋時代晩期)、青森県大石平遺跡出土土製品(重要文化財・縄紋時代)、愛知県松河戸遺跡出土土人形(弥生時代前期)、愛知県朝日遺跡出土木製品(弥生時代中期)、愛知県朝日遺跡出土土器(弥生時代後期)、滋賀県烏丸崎遺跡出土木偶(弥生時代中期)[出品総数448点、うち重要文化財・重要美術品87点] ●学芸員による展示解説:毎週日曜日・祝休日のAM11:00から特別展示室にて |
●関連イベント:
|
| 古代研究の、いま -シンポジウム- |
●ところ:奈良女子大学記念館講堂(近畿日本鉄道奈良駅下車、北へ徒歩5分)
●日時:1998.4.4(土) PM1:00~
●問い合わせ先:古代学学術研究センター設立準備室(奈良女子大学文学部比較歴史社会学研究室内) 〒6308506 奈良市北魚屋西町、TEL&FAX0742-20-3319
●報告:松井章(奈良国立文化財研究所)・佐藤宗諄(奈良女子大学、古代史学)・奥村悦三(奈良女子大学、古代国語学)
●討論:司会 広瀬和雄(奈良女子大学、考古学)
| シンポジウム「中世集落と潅漑」 -歴史資料(遺跡・文献)は何を語るか- |
●ところ:奈良大学C302教室(奈良市山陵町1500)
●日時:1998.3.28 PM1:00~PM4:45(AM12:30開場)、1998.3.29 AM10:00~PM4:45(AM9:30開場)
●申し込み:参加申込書を下記まで郵送。申し込み締め切りは3月20日(必着)。ただし、参加希望者が300名に達した時点で締め切りとなる。
●申込書送付先:〒634-0042 奈良県橿原市菖蒲町1-31-7-2 山川均
●会場までの交通案内:近畿日本鉄道高の原駅より奈良交通バスにて「奈良大学前」下車。
●内容:「中世集落」、中世の「潅漑」をテーマにして、関連諸分野の研究者たちによる学説、とくに異分野の研究間における「高次元の融合」を目標とする。
●3月28日の内容:
基調講演1:「中世集落と潅漑への接近法」金田章裕(京都大学)
基調講演2:「中世村落の展開」広瀬和雄(奈良女子大学)
懇親会(PM5:30~PM8:00、奈良大学食堂にて)
●3月29日の内容:
個別研究1:「中世集落と耕地開発」山川均(大和郡山市教育委員会)
個別研究2:「潅漑と環濠屋敷(仮題)」今尾文昭(奈良県立橿原考古学研究所)
個別研究3:「民俗学視点からみた大和の中世集落の潅漑考」浦西勉(奈良県立民俗博物館)
個別研究4:「中世低地集落の歴史的位置」石尾和仁(徳島県立埋蔵文化財センター)
個別研究5:「中世荘園と村落」水野章二(滋賀県立大学)
シンポジウム:司会・コーディネイト/水野正好(奈良大学)・水戸雅寿(安土城城郭調査研究所)、進行/植野浩三(奈良大学)・近江俊秀(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館)
●主催:シンポジウム「中世集落と潅漑」実行委員会、共催:奈良大学文学部考古学研究室
※参加申込書の様式は次のとおり(ヨコ18㎝・タテ11㎝程度)
(TABLE内背景色使用のため、NN3.0x以上でないとうまく表示できません)
住所〒 所属 |
| 南都の法会 連続講演会第1回 東大寺の法会 |
●ところ:奈良女子大学G101教室(近畿日本鉄道奈良駅下車、北へ徒歩5分)
●日時:1998.3.14(土) PM2:00~ (PM1:00から記録ビデオを上映)
●参加費:無料
●講師:佐藤道子(東京国立文化財研究所名誉研究員)・永村眞(日本女子大学教授)
●問い合わせ先:奈良女子大学文学部日本アジア言語文化学研究室 〒6308506 奈良市北魚屋西町、TEL&FAX0742-20-3279

|
●ところ:千里協栄生命ホール(北大阪急行電鉄・大阪モノレール千里中央駅下車徒歩5分) ●日時:1998.3.7(土) PM1:00~PM4:00 ●定員:400名(先着) ●費用:300円(資料代) ●申し込み締切:1998.3.5 ●申し込み:ハガキまたはFAXにて、1.電話・2.氏名・3.年齢・4.電話番号・5.人数を記入の上、「セミナー申込み」と明記して日本民家集落博物館まで申し込む。 ●申し込み・問い合わせ先:日本民家集落博物館 〒5600873 豊中市服部緑地1-2、TEL06-862-3137 FAX06-862-3147 ●備考:当日は、手話通訳・保育(要予約)も利用可能。 ●講師:岡本健一(毎日新聞編集委員)・鳥越憲三郎(大阪教育大学名誉教授)、若林弘子(建築史家) ●内容:全国各地の民家を移築保存している日本民家集落博物館では、日本民家のルーツともいえる古墳時代の家屋の復元模型の作製・展示を行っている。昨年の「高屋」に引き続き、2作目の「高殿」が完成した。この模型の完成を記念して、日本古代の神殿の形式やまつりと政治のあり方をテーマにしたセミナーを「博物館都市・大阪」の形成をめざす大阪21世紀協会とともに開催する。 第1部 基調講演 「古代神殿について」鳥越憲三郎(大阪教育大学名誉教授) 「神殿の構造について -復元模型の製作を中心に-」若林弘子(建築史家) 第2部 鼎談 「古代日本の祭政について」岡本健一(毎日新聞編集委員)・鳥越憲三郎・若林弘子 |
●特別展示「行基菩薩と北摂」(※この展示は終了しました。)
●ところ:池田市立歴史民俗資料館
●期間:1997.10.18~11.9&11.12~12.7
●休館日:月曜日・火曜日・月末・11.23
●開館時間:AM9:00~PM5:00
●交通案内:阪急宝塚線池田駅下車徒歩13分
●駐車場:図書館との共同の無料駐車場があり、数台は駐車可能。満車の場合もある。
●入館料:無料
●問い合わせ:同館(TEL:0727-51-3019 ZIP:563 池田市五月丘1-10-12)
●内容:池田市内の八ヶ所の寺に行基伝承が残されていることに注目して、行基の事蹟と北摂との関わり、行基伝承の成立と展開、池田に伝わる行基の伝承という3つの視点から構成。
現在に伝えられている行基に関する直接資料や同時代の出土遺物、行基伝承を描いた絵巻や行基の画像などの絵画資料、行基伝承の成立に関連する歴史資料などを展示。
なお、前期・後期で一部展示替えをおこなう。●記念講演会
日時:11月9日(日)PM1:30~(聴講無料)
「行基の伝道と社会施設造り」 井上 薫 氏(大阪大学名誉教授)

|
平成9年度企画展 「TK73 -作り始められた頃の須恵器-」 (※この展示は終了しました。) ●ところ:大阪府立泉北考古資料館 ●期間:1997.7.15~10.12 ●休館日:月曜日 ●開館時間:AM9:00~PM4:30(入館はPM4:00まで) ●交通案内:南海なんば駅から和泉中央行きの電車に乗車し、泉北高速鉄道泉ヶ丘駅下車。徒歩8分 ●駐車場:なし(どうしても自動車で行きたい場合は、泉ヶ丘駅前の駐車場ビル(有料)を利用しましょう) ●入館料:無料 ●問い合わせ:同館(TEL:0722-91-0230 大阪府堺市若松台2-4 大蓮公園内) ●内容:田辺昭三氏の陶邑須恵器編年において、5世紀前半に日本で須恵器が焼き始められた最初のころの須恵器の標式資料となっている窯が、TK73号窯(高蔵寺73号窯)である。今回の企画展では、このTK73号窯出土須恵器と、陶邑窯跡群内の他の初期須恵器を展示。 ●主要展示品:TK73号窯出土須恵器・TG232号窯(大庭寺遺跡)出土須恵器・ON231号窯(野々井西遺跡)出土須恵器 |
●夏休み特別展示「遺跡を再現」(※この展示は終了しました。)
●ところ:神戸市埋蔵文化財センター
●期間:1997.7.26~8.31
●休館日:月曜日・休日の翌日
●開館時間:AM10:00~PM5:00(入館はPM4:30まで)
●交通案内:三宮駅から:神戸市営地下鉄に約30分間乗車し、西神中央駅で下車、徒歩約5分。明石駅から:神戸市バス・神姫バスに約35分間乗車し、西神中央駅で下車、徒歩約5分。
●駐車場:ショッピングセンター・プレンティなどの駐車場(有料?)を利用すればOKかな?
●入館料:大人100円、小・中学生50円
●問い合わせ:同館(TEL:078-992-0656・0657 FAX:078-992-5201 ZIP:594 神戸市西区糀台6丁目 西神中央公園内)
●主催:神戸市教育委員会 協賛:プレンティ
●内容:近畿地方の主要な遺跡において、保存科学処理を施して取り上げをおこなった遺構・遺物を展示。
●主要展示品:東大寺土層断面、白川火葬墓、飛鳥寺西門地区土管暗渠、本薬師寺西塔基壇断面、坂田寺仏堂壁体断面、藤原京トイレ断面、頭塔心礎断面、粟津湖底遺跡貝塚断面、正楽寺遺跡縄文人骨、難波宮朱雀門柱穴、山之内遺跡ナウマン象足跡、狭山池北堤断面(狭山池北堤窯灰原部分)、西求女塚古墳地滑り断面、垂水日向遺跡縄文人足跡。●講演会
日時:7月27日(日)PM2:00~PM4:00(先着順170名まで)
「発掘現場から博物館へ」 沢田 正昭 氏(奈良国立文化財研究所研究指導部長)●展示解説
日時:7月26日(土)PM3:00~・8月9日(土)PM3:00~

●平成9年度春季特別展
「青銅の弥生都市(テクノポリス) -吉野ヶ里をめぐる有明のクニグニ-」(※この展示は終了しました。)
●ところ:大阪府立弥生文化博物館
●期間:1997.4.19~6.29
●休館日:月曜日(ただし、5.5は開館、5.6は閉館)
●開館時間:AM10:00~PM5:00(入館はPM4:30まで)
●交通案内:JR阪和線天王寺駅から25分、信太山駅下車徒歩7分、南海本線松ノ浜駅下車徒歩20分
●駐車場:あり
●入館料:大人600円、中学生以下と65歳以上は無料
●問い合わせ:同館(TEL:0725-46-2162 ZIP:594 大阪府和泉市池上町443)
●内容:佐賀県吉野ケ里遺跡の発掘調査とそれ以後の調査成果によって、多くの新しい事実が判明しつつある。また、玄界灘沿岸の弥生時代のクニグニとくらべて、いままであまり注目されなかった有明のクニグニの姿が明らかになってきている。今回の展示は、最新の発掘調査成果を集め、吉野ヶ里をめぐる有明のクニグニの姿を探るものである。
●主要展示品:吉野ケ里遺跡=最大級墳墓出土品一括・最大級の甕棺・青銅器鋳型、鳥栖市安永田遺跡出土鋳型一括、朝鮮系土器多数、各種青銅製利器多数、青銅鏡多数、朱漆塗り鞘付き銅剣レプリカ、装身具類多数。
●歴史セミナー
時間:PM2:00~PM4:00(受付開始:PM1:00) 会場:1階ホール
○5月11日(日)
「有明の世界」 高島 忠平 氏(佐賀県教育庁)
○5月25日(日)
「国産青銅器の開始と展開」 岩永 省三 氏(奈良国立文化財研究所)
○6月8日(日)
「自然科学からみた古代青銅器」 平尾 良光 氏(東京国立文化財研究所)
○6月22日(日)
「九州の銅鐸と出雲の銅鐸」 難波 洋三 氏(京都国立博物館)